子どもの夢は将棋士
子どもの夢はコロコロ変わるものと相手にせず
子どもの夢はコロコロ変わるものですよね。
うちの子はもともと電車の運転士が夢でしたが、小1から1番の夢は将棋士になりました。
今後もかわっていく可能性が高いです。
それに、将棋ってチェスやオセロと同じで「遊び」の一種です。
最初は手作り「どうぶつしょうぎ」から始め、
小学校入学後、本物の将棋を教えましたが、
(↑入門書と将棋入門の動画サイトを載せています。)
shimausj.hatenablog.com
(↑入門書と無料アプリのことを書いています。)
教養のひとつとして遊び方を覚えてくれればいいなと思っていただけなので、
最初は「遊んでお金もらう気なの~?」と相手にしていませんでした。
すぐに飽きるだろうと思っていたし、できるだけ他の遊びをするように促していました。
子どもからタイムリミットがあることを告げられる
ところがある時、小2になった子どもに「18歳までに四段をとらないといけないって知っている?」(※正確には違います)と聞かれ、《ええ?そうなの?、大人になってからどうしても夢があきらめきれなくて…と、なれるものではなかったの?》という気分になり、しっかり職業としてとらえ、将棋士になる方法まで自分で把握しているんだったらという気持ちになりました。
将棋士になるには?~物理的に大人になってから就ける職業ではない
実際、18歳までに4段をとらなといけないかと調べてみたら、そうではなかったのですが、もっと厳しい内容でした。
プロの将棋士になるには、まず公益社団法人日本将棋連盟の奨励会に入会して四段まで昇段しなければならない。プロ将棋士の弟子になり推薦を受けるか、小中学生対象のアマチュア大会での好成績を残して推薦を免除された19歳以下の者に入会試験の資格が与えられる。奨励会に入会する年齢層は、小学校高学年が一般的で、奨励会員は満21歳の誕生日までに初段、満26歳の誕生日までに四段になる必要があり、常に腕を磨き続ける必要に迫られる厳しい世界といえる。
(将棋棋士(しょうぎきし)になるには|大学・専門学校のマイナビ進学より引用)
小学校高学年が一般的…本当にタイムリミットが迫っています!
このままでは夢を潰したと言われかねない状況です~!
※追記です。
中学生の時に奨励会に不合格で…奨励会に入らないままプロ入りされた方が出てきました。
いくつになってもやり直しができると希望を与えてくれるニュースですね!
厳しい世界!とりあえず定跡本を!
しかし、厳しい世界に勝ち抜けるのはごく一部。将棋好きの子どもは多いし、私は1%もないくらいの確率だと思っています。
将棋教室やネット対戦で強い人がたくさんいるのがわかると、気持ちがかわるかもしれないですし…。
すぐに将棋教室に通わせればいいのですが、
うちの子は、コロナが流行っているからと今までご機嫌で通っていた英会話教室を自分からやめると言い出したくらいで、「コロナが落ち着いたら将棋会館へ行ってみたい」と言っています。
また、ネット上での対戦は大人向けのものだからと夫はいい顔しません。
う~んと悩んでいると、
「将棋会館の将棋教室へはコロナが落ち着いたら通うとして、とりあえず定跡本を与えて定跡を覚えさせてはどうか?それが無理なら確実に将棋士にはなれないんだし」と夫からの提案がありました。
そもそも定跡(定石)とは?
将棋に詳しくない私は「定跡本とはなに?」と夫に聞くと「将棋の教科書のようなもので、まず基本の形を覚えておくことが必要」ということでした。
ネットで調べてみると次のように書いていました。
(囲碁で)定石、(将棋で)定跡(じょうせき)とは、昔から研究されてきて最善とされる、きまった手の打ち方[1](一連の手)。囲碁や将棋に限らず、アブストラクトゲーム全般に広く存在する概念・用語であり、石を用いる囲碁、オセロ、連珠などでは「定石」と「石」という漢字を用い、駒を用いる将棋、チェスなどでは「定跡」と「跡」という漢字が用いられる。チェスでは「オープニング」とも。
(定石 - Wikipediaより引用)
囲碁と将棋では漢字が違うのが面白いですね。
それらしき本をネット検索して探し、とりあえず図書館でバーッと予約し借りることしにしました。
今回はその本をご紹介したいと思います。
将棋の教科書【定跡本】
羽生善治の定跡本
今は藤井聡太さんが大人気ですが、一昔前は羽生善治さんが人気を誇っていましたよね。子どもも羽生さんより藤井聡太さんの方がいいと言っていますが、親世代のおすすめはやっぱり羽生さん!
「羽生善治の定跡の教科書」
そのまんまのタイトルですね!


羽生さんの本はどれもわかりやすく、子どもは好んで読みます。

「羽生善治の将棋入門ジュニア版」
羽生善治さんは子ども向けの本も数多く出されています。
図書館で次の本を借りたのですが…



中身はいいのですが、同じものがネット上で見つかりませんでした。
似たタイトルのものが出てきてレビューを読んでみると、絶賛されていました。
よろしければご参考に。
大人の私にも十分な入門書であり、教科書として使えます。
文体も、特に子供向けのような口調ではなく、大人が読んで違和感がなかったです。
この本に書いてあることを一般の将棋の本で探すとなると、何冊かになるし、
探すのも難しいのでは?と思いました。
加えて、内容の絞り込みもあり、一冊で語り尽くしているので、無駄もなく、
読んで身につくと言えるのではないでしょうか。
(Amazon商品レビューより引用)
辞典(事典)的なもの
「将棋戦法事典100+」
まだ入手していませんが、比較的新しいものでは次の本が良さそうです。
上の続編です。

将棋世界Special 将棋囲い事典100+ ~エルモ! 新型雁木! 羽生流右玉! 基本形から最新形まで超収録!~ (マイナビムック)
- 作者:将棋世界編集部
- 発売日: 2020/12/16
- メディア: ムック
他にも最新の将棋の事典・辞典系の本がたくさんあり、Amazonのレビューを見ていたら、雑誌的に最新のトレンドの型を紹介しているものよりも、古いけれど「将棋戦法小辞典」が良いという書き込みがありました。
「将棋戦法小辞典」
早速、図書館からかりてきたのですが…相当古い雰囲気を醸し出していました。
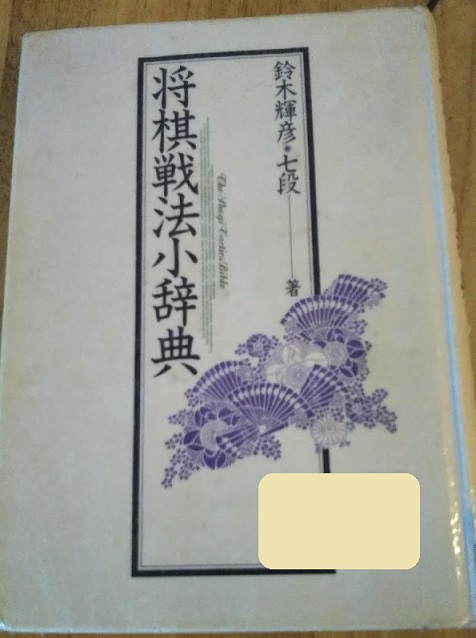
大人向けのシブイ表紙です。


うちの子は羽生善治さんの本の方から読み始めました。
内容はとてもいいけれど、かなり戦法が古いものしか載っていないようです。
ほとんどの戦型が載っています。この本を何回も熟読したら初段の道も遠くないでしょう。
辞書代わりに使うのもいいかもしれません。
但し、刊行が古いため、藤井ステム、ゴキゲン中飛車、中座飛車等の戦法は載っていません。
(その代わりに対振り飛車の位取り作戦等の現在ではあまり見られない戦型が載っています)
ゴキゲン中飛車や石田流のような最新系の将棋は載っていない
(Amazonの商品レビューより引用)
続編もあります。
小学校低学年にはちょっとハードルが高いかもしれません。
うちの子は全部他のものを読みつくしたあと、読んでいました。
わかりやすくコンパクトなもの~将棋のルールを覚えた後のステップに
「全戦法対応 将棋・基本定跡ガイド」~1番おすすめの本
「全戦法対応 将棋・基本定跡ガイド」は、一手一手丁寧にとてもわかりやすく書かれていて、コンパクト。持ち運びしやすく子どもに大好評でした。

A4の用紙の上に置いてみました。

おおよそA4の4分の1くらいの大きさですね。この本が他の本よりコンパクトで持ち運びしやすい大きさだということがお分かりいただけると思います。
基本的な戦法が載っているようです。
うちの子はだいたい知っていたけれど「石田流…」などを知らなかったそうです。
これからたくさん学ぶとしても基本は押さえておきたいでしょうし、
「将棋を指す上で覚えておくべき戦法の駒組み手順を次の一手形式で丁寧に解説」
「将棋のルールを覚えたあと、次のステップに進みたいという人に」
こんな風に書かれているんですが、本当にその通りの本。
コンパクトなので外遊びにも持って行けます。(置き忘れてこられると困りますが…)
今のところ、低学年のお子さんの最初の一歩としては、これが一番のおすすめです。
また他のおススメが見つかれば別の記事にしてみます。
囲碁の世界は?
図書室から囲碁入門もかりてきた
以前、将棋と同様、教養のつもりで囲碁も教えました。
囲碁の入門動画を次の記事に載せています。
将棋好きになり始めた頃、学校の図書室にある将棋の本は次のようなマンガも借りて、
借り尽くし、新しく借りるものがなくなったからと、次のような本を借りてきたことがありました。
「はじめての囲碁入門」~これですべてOK!
地味な表紙ですが

この本は犬や猫のキャラクターが出てきて馴染みやすく、

初歩の部分から書いていて、

まったく初めての子でも一人でできるようになっていました。

最終的にはしっかりと囲碁がうてるようになります。

以前、囲碁の入門動画を見せたり囲碁教室に連れて行ったりしましたが、これ一冊で済むじゃないかと思ってしました。この本はかなりおススメです!
囲碁と将棋、どっちの方がいい?
私はもともと囲碁の方が海外でも戦えて面白そうだと思っていたので、将棋士になりたいと聞いた時、どうせなら囲碁の方がよかったのにと思ってしまいました。
囲碁の世界も厳しいと思いますが、将棋ほど人気がないので国内では競争率が低い気がしますし。
⇒囲碁の方が世界でメジャーなのに、将棋より人気がない理由 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン
今から仲村菫さんのようにはなれませんが…。
仲邑 菫(なかむら すみれ、2009年3月2日 - )は、日本棋院東京本院所属の囲碁棋士、初段(2019年4月)。東京都出身。仲邑信也九段門下。2019年4月、日本棋院の棋士採用試験で新設された英才特別採用推薦棋士第1号として入段し、日本棋院に所属する棋士のプロ入り最年少記録(10歳0か月)を樹立した[1][2][3][注 1]。
師匠の仲邑信也は父親であり[4]、母親の妹である叔母は辰己茜である。母親は元囲碁インストラクターでもある
( 仲邑菫 - Wikipediaより引用)
ご両親も囲碁の世界の人で本場韓国に留学した経験があるなんて、卓球の福原愛ちゃんみたいですね。私も何か英才教育しておけば良かった~!
まぁでも、夢をかなえるのはごく一部の人。子どもが「親は自分の夢をいつも出来る範囲で精一杯応援してくれた」と思ってくれれば、それいいですよね。
☟下のバナーをクリックしてくださると嬉しいです。
3つのカテゴリーに参加しています。
いつも応援ありがとうございます!!!









